相続財産に含まれる「未収金」とは?

相続が発生すると、現金・不動産など目に見える資産だけでなく、被相続人が生前に保有していた一切の権利義務を洗い出す必要があります。こうした“書類上の財産”は気付きにくく、国税庁統計では現金・預貯金の申告漏れが多いとされていますが、帳簿上の債権である未収金も見落としが生じやすい項目です。
なかでも売掛金や家賃の未収金は、すでに発生しているにもかかわらず入金が死亡後になるため、放置すると追徴課税のリスクが高まります。
本記事では未収金の定義・評価方法から申告フロー、回収後の税務処理までをまとめて解説します。
未収金とは何か

未収金の定義と代表例
未収金とは、被相続人が生前に締結した契約から生じ、相続開始時点(死亡日)までに確定しているが未回収の債権を指します。
| 代表例 | 具体的なケース |
|---|---|
| 家賃の未収分 | 賃借人が振込期日を過ぎても当月分を支払っていない |
| 売掛金 | 商品を納品済み・請求書発行済みだが支払期日前に死亡 |
| 貸付金の元利 | 返済期日到来分が未入金 |
| 配当金・利息 | 権利確定日は到来、支払日は死亡後 |
未収金は発生主義で考える
相続税評価では発生主義を採用します。債権が確定していれば、現実の入金有無は問いません。
相続税上の取り扱い
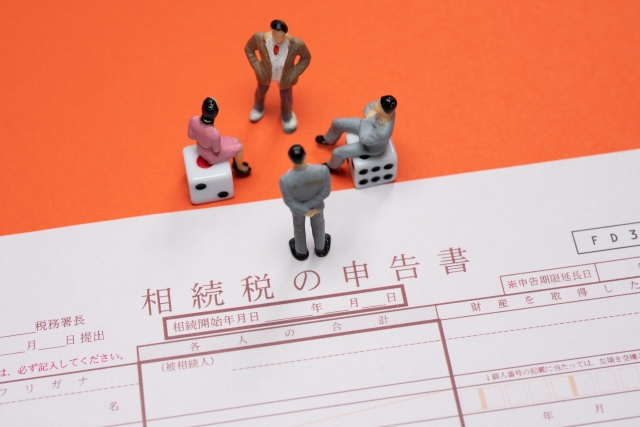
法律と通達を確認
- 相続税法第3条:被相続人が亡くなった時点で保有していた「すべての財産」が課税対象になります。ここには、まだ振り込まれていない家賃や売掛金などの未収金(債権)も含まれます。
- 財産評価基本通達:未収家賃や売掛金は「金銭債権」として評価し、原則として額面(請求額)どおりに課税価格へ算入します。
個人事業主と賃貸オーナーが気をつけるポイント
- 死亡日が決算前でも要カウント
例:青色申告の決算が12月末でも、10月に亡くなった場合は10月までに発生していた売掛金や未収家賃をすべて相続財産に含めます。 - 所得税で現金主義でも、相続税は発生主義
普段の所得税申告で「現金主義」(実際にお金を受け取った時点で収入計上)を選択していても、相続税では必ず「発生主義」が適用されます。つまり、まだ入金されていなくても、請求書の発行などにより金額が確定している債権は、その時点で相続財産として評価しなければなりません。
未収金の評価額を決める3ステップ
| ステップ | 具体的な作業 | 簡単な例 |
|---|---|---|
| ① 額面評価 | 請求書や契約書で確認した金額をそのまま記載します。 | 売掛金120万円 ⇒ 120万円で計上 |
| ② 貸倒見積高の控除 | 回収不能リスクを示す客観資料(督促記録・破産手続開始通知など)があれば、その分を控除できます。 | 請求額100万円 × 回収見込み70% ⇒ 評価額70万円 |
| ③ 備忘価額 | 回収可能性がほぼゼロの場合は1円だけ課税価格に入れ、もし後日回収できたらその年の所得税で申告します。 | 旧取引先が倒産 → 評価額1円/3年後に30万円回収 ⇒ その年の一時所得 |
ポイント:貸倒見積高を差し引くには、口頭の説明ではなく、督促状・債務者の決算書・破産公告といった”客観的な証拠”が不可欠です。
- 額面評価:原則として請求額=評価額。
- 貸倒見積高の控除:回収不能リスクを客観資料で証明できれば評価減。
- 例:額面100万円/回収見込み70% → 評価額70万円
- 備忘価額:回収可能性が極めて低い場合は1円計上し、後日回収分を所得税で処理。
申告までの3ステップ・チェックリスト
| ステップ | やること | チェックポイント |
|---|---|---|
| ① 資料収集 | 契約書・請求書・売掛台帳・督促状を保管 | 債権の成立根拠が書面で確認できるか |
| ② 残高確定 | 死亡日時点の未収残高を抽出 | 通帳・会計ソフト・エビデンスを突合せ |
| ③ 専門家連携 | 税理士に評価額と貸倒リスクを相談 | 必要に応じて弁護士・司法書士と協働 |
申告期限は死亡から10か月。準備に思いのほか時間がかかるため、早めの着手が鉄則です。
未収金を回収した後の税務処理
| シチュエーション | 税目 | 申告時期 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 相続開始後に回収 | 所得税(雑所得/事業所得) | 回収した年の確定申告 | 相続財産ではない点に注意 |
| 回収不能が判明 | 相続税 | 更正の請求(5年以内) | 評価額を減額し税額還付を受ける |
準確定申告との違い
- 準確定申告(死亡日までの所得)には死亡後の回収分は含めない。
- 相続税と所得税の二重課税が起きないよう、専門家に確認を依頼しましょう。
まとめ

未収金は帳簿の片隅に潜む“隠れ資産”です。申告漏れ=追徴課税という厳しい現実を避けるためにも、
- 発生主義で債権を洗い出す
- 貸倒リスクを客観資料で裏付ける
- 10か月の申告期限内に専門家と申告書を完成させる
この3点を徹底しましょう。早期に専門家へ相談し、追徴リスクをゼロに近づけていきましょう。
相続の申告でお困りの方は
相続申告コンシェルジュにご相談ください。
※24時間受付中
お電話でもお気軽にどうぞ!
03-6666-1954
※受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日休)

