相続人が認知症。遺産相続はどうなる?生前対策について
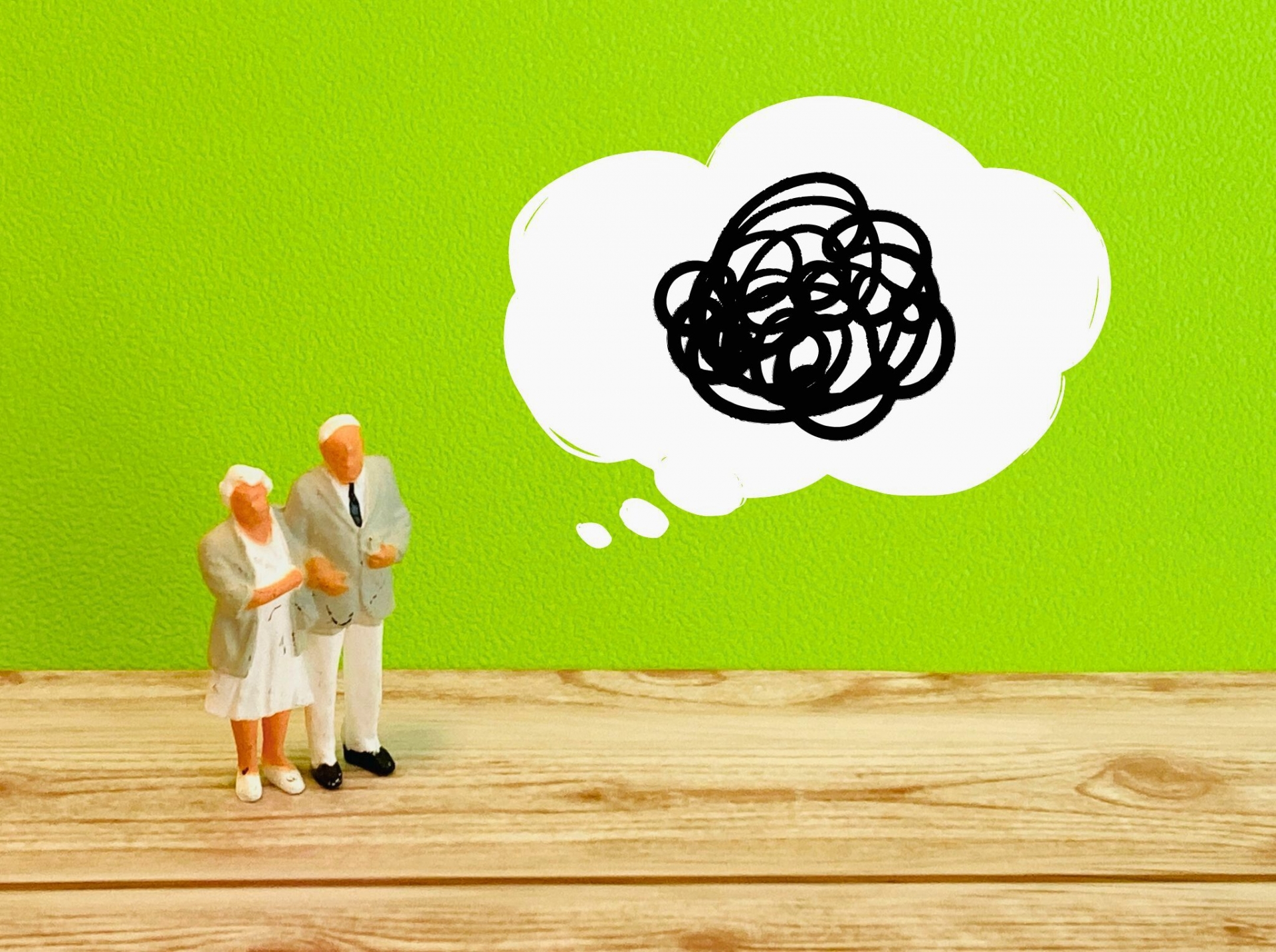
こんにちは。
江東区・相続申告コンシェルジュ
大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。
認知症のご家族がいる場合、相続がどうなるのかと不安を感じている方は少なくありません。
今回は、認知症のご家族がいる場合、相続においてどういった点が問題となるのか、また生前対策や注意点についても紹介しましょう。
認知症のご家族が相続人になる問題点

被相続人が亡くなった場合、相続人が認知症の家族だった場合、相続手続きに以下のような支障が起こりえます。
- 遺産分割協議ができず、財産が凍結
- 代筆で罪に問われる恐れ
- 相続放棄ができない
それぞれの問題点について解説します。
遺産分割協議ができず、財産が凍結
相続が発生すると、被相続人の財産は凍結され、銀行口座などからお金を下ろすことができません。
また、不動産の処理も不可能となります。
本来は遺産分割協議で相続人を確定できれば、凍結の解除が可能です。
しかし、認知症の方の判断能力が低下している場合、相続人全員で合意が必要となる遺産分割協議に参加できません。
そのため、相続人に認知症の方がいると全員の合意が得られず、凍結の解除ができなくなってしまい、不動産などの売却もできなくなってしまいます。
代筆で罪に問われる恐れ
認知症の相続人に代わって勝手に遺産分割協議書などに代筆して署名することはできません。
もし代筆が判った場合は、私文書偽造の罪に問われる恐れがあります。
トラブルの原因にもなりかねないため、代筆は絶対にやめましょう。
認知症の相続人は相続放棄できない
判断能力が低下している認知症の方は、法律行為ができません。
たとえば、相続放棄などといった判断もできなくなります。
その場合でも、他の相続人が本人に代わって、家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをしても、受理されることはありません。
認知症の相続人がいる場合の生前対策
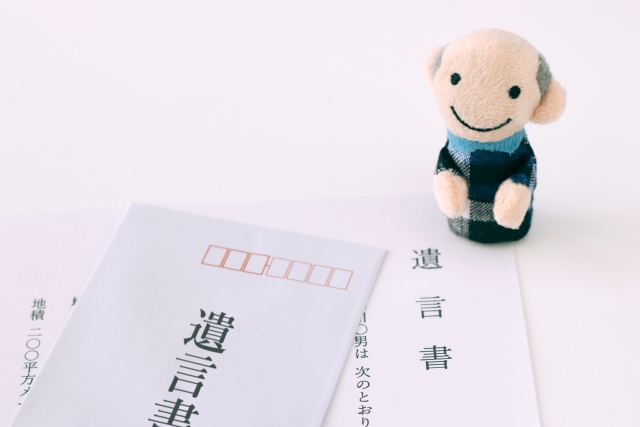
高齢化社会が進み、今後相続人が認知症であるケースは増えていく可能性は高いです。
相続でのトラブルを回避するためには、以下の対策を講じておきましょう。
- 遺言書を作成する
- 家族信託をする
- 生前贈与をしておく
それぞれの対策について解説します。
遺言書を作成する
ご家族内に認知症の方がいる場合は、生前に遺言書を作っておきましょう。
遺言書の中で、誰に何をどのくらい相続させるのかなどを決めておけば、遺産分割協議をしなくても財産の凍結を解除して、相続手続きを進めることが可能です。
不動産や預貯金について確実に記載しておきましょう。
家族信託をする
たとえば、被相続人となる方とその子どもが家族信託をしておけば、遺産分割協議を回避できます。
継承先を定めておき、被相続人となる方が亡くなった後、子どもが契約通りに財産を管理・運用・処分することができます。
そのため、遺産分割協議の必要はありません。
生前贈与をしておく
預貯金や不動産などの財産を生前のうちに継承する、生前贈与も一つの方法です。
ただし、控除額以上の贈与を行うと、贈与税がかかってしまうので注意しましょう。
被相続人が認知症だった場合の注意点

反対に、亡くなった方・被相続人が認知症だった場合、遺言書の内容に対して異議を申し立てる相続人が出る可能性があります。
たとえば、被相続人である父親が亡くなった際、長男にほとんどの財産を相続させる旨の内容が記載されていた場合、納得のいかない次男などから「父は認知症で判断能力がなかった、だからこの遺言書は無効だ」と言われてしまうかもしれません。
もしその主張が受け入れられてしまうと、相続人全員で遺産分割協議が必要です。
そこで合意を得られなければ、トラブルが泥沼化し、裁判へと発展していく可能性もあります。
そのため、遺言書の作成も、元気なときに行うのが重要です。
高齢になってきて、物忘れが多くなってきたなと感じた場合は、役所を利用したり、医師から意思や判断能力があることを証明する診断書をもらっておくといいでしょう。
認知症になる前、元気なうちに遺言書を書こう

ひとまず、遺言書は元気なうちに作成することが重要です。
遺言書があるだけで、相続手続きをスムーズに進められ、相続人同士の争いも防ぐことができます。
特に、お子さんや配偶者に面倒を見てもらおうと考えている場合は、家族に負担がかからない状況にできるように準備しておくといいでしょう。
相続の申告でお困りの方は
相続申告コンシェルジュにご相談ください。
※24時間受付中
お電話でもお気軽にどうぞ!
03-6666-1954
※受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日休)

大倉公認会計士税理士事務所所長
大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。
会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。
「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。

