空き家を相続したらすぐにやるべき5つのこと
日本の空き家問題は、今や社会全体の課題となっています。特に近年は高齢化の進行により、親から子へと空き家が相続されるケースが急増しています。国土交通省の統計によれば、全国の空き家数は年々増加傾向にあり、相続をきっかけに所有者となった方が戸惑うケースも少なくありません。
空き家は放置すると、建物の老朽化や防犯上の問題、さらには近隣住民とのトラブル、税制上の不利益など、さまざまなリスクを抱えることになります。
そこで本記事では、「空き家を相続したらすぐにやるべき5つのこと」と題し、相続直後に取るべき重要なアクションを解説します。
相続登記を済ませる

まず最初に行うべきは、相続登記の手続きです。
2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。この義務化は、相続人が不明な不動産が増加し、地域の防災や土地活用に支障をきたすケースが増えたことが背景にあります。
相続登記の手続きには、被相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、不動産の固定資産評価証明書などが必要です。手続きは法務局で行えますが、相続人が複数いたり、遺産分割協議が複雑な場合は、司法書士などの専門家に依頼することで円滑に進められます。
空き家の状態を確認・管理する
登記が済んだら、次に建物の状態確認と管理を始めましょう。
空き家は放置することで急速に劣化が進み、倒壊や雨漏り、シロアリなどの害虫被害が発生するリスクがあります。また、衛生面や景観の悪化により近隣住民とのトラブルにつながることもあります。
建物内の換気、簡易清掃、庭木の剪定、防犯対策など、定期的なメンテナンスを行うことが重要です。遠方に住んでいる、あるいは管理の時間が取れない場合は、空き家管理サービスを活用するのも一つの手段です。月額数千円で巡回・清掃・簡易補修を行ってくれる業者も存在します。
固定資産税・都市計画税の確認

空き家であっても固定資産税や都市計画税の納税義務は発生します。
これらの税金は、毎年1月1日時点の所有者に課税され、市区町村から納付書が送付されます。
住宅用地であれば「住宅用地特例」により税額が軽減されますが、建物が老朽化して居住不能な状態や、解体後の更地になるとこの特例が適用されず、税額が数倍になるケースもあります。
また、「特定空き家」に指定されると、特例が外されるだけでなく、行政代執行による解体費用の請求が行われることもあるため注意が必要です。
利活用・売却の方針を検討する
空き家を今後どうするかを早い段階で検討しましょう。選択肢としては、賃貸に出す、売却する、自分で住む、民泊やシェアハウスとして活用するなどがあります。ただし、民泊やシェアハウスは自治体によって制限がある場合があるため、事前の確認が必須です。
方針を決めるには、地域の不動産市況を調べることが重要です。築年数や立地によっては買い手がつきにくいケースもあるため、不動産会社や空き家相談窓口に相談して、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。場合によってはリフォームや解体も検討することもあります。
空き家に関する補助金や制度をチェック
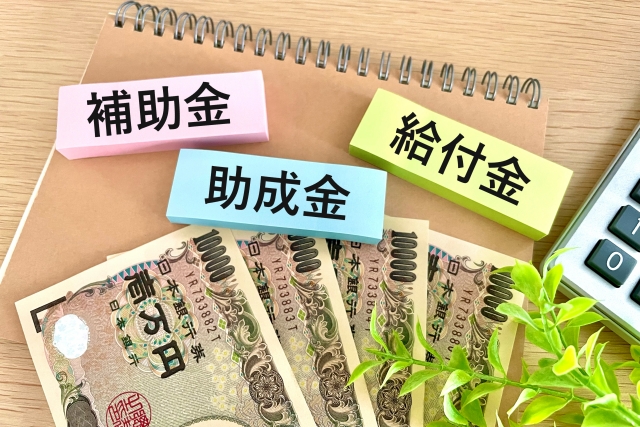
近年、空き家対策として各自治体がさまざまな補助制度を設けています。空き家バンクへの登録、老朽空き家の解体費用の一部を負担する助成金、リフォーム費用の補助、利活用に関するマッチング支援など、活用できる制度は多岐にわたります。
まずは、空き家の所在地を管轄する市区町村のホームページを確認し、利用可能な制度を把握しましょう。また、「空き家ポータルサイト」などで検索すると、国土交通省の空き家対策ページも見つけることができます。
おわりに

空き家を相続したら、登記、管理、税務、利活用の検討、補助金制度の確認と、やるべきことが多岐にわたります。これらを放置してしまうと、思わぬトラブルや経済的損失を招く可能性があります。
相続した空き家は、単なる負債ではなく、賃貸収入や譲渡益などを通じて有効な資産にもなり得ます。早期に対応し、必要に応じて専門家の力を借りながら、空き家を有効に活用していきましょう。
相続の申告でお困りの方は
相続申告コンシェルジュにご相談ください。
※24時間受付中
お電話でもお気軽にどうぞ!
03-6666-1954
※受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日休)

